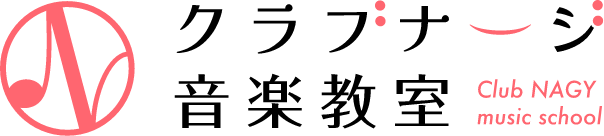変奏曲とは何ぞや?どんな曲がある?(後編)
2019.09.13音楽のマナビ

変奏曲とは、長短さまざまな主題(テーマ)または旋律を、カタチを変えながら繰り返す形式です。
後編では、前編に引き続き変奏曲の名曲と、変奏曲の分類についてもお話しようと思います。
変奏曲の名曲
チャイコフスキー「ロココの主題による変奏曲」
実質的にはチェロ協奏曲となっています。ロココ風の主題(モーツアルト時代のスタイル)はチャイコフスキーの自作になります。
ラフマニノフ「コレルリの主題による変奏曲」
スペインの古い旋律「ラ・フォリア」が、ロシア風味付きで変奏されます。
レーガー「モーツアルトの主題による変奏曲」
有名なモーツアルトの主題が仰々しく、こってりとした味わいで展開されています。
ウェーベルン「ピアノのための変奏曲」
調性のない、人為的に構築された音列がこねくり回されます。非常に難解な曲です。
シェーンベルク「管弦楽のための変奏曲」
12音技法(調性のない曲を書くための技法)で書かれた変奏曲で、主題と9つの変奏、終曲からなっています。
ウェーベルンの作品と同じく、一般人には難解な曲であるといえます。
以上が、変奏曲の名曲の数々です。
一言で「変奏曲」と言っても、様々な変奏の仕方があることがお分かりいただけたかと思います。
続いて、変奏曲における変奏の分類についてお話していきます。
変奏曲の分類
変奏曲における変奏の仕方は、大きく分けて以下の2つのタイプに分類されます。
① ほとんど原型から逸脱しない変奏
古くからある伝統的な変奏で、「単純変奏」と呼びます。
前編で紹介した、モーツアルトの「キラキラ星変奏曲」がこのタイプに該当します。
② テーマの原型から大きく逸脱する展開をみせる変奏
曲が進むにつれて、だんだんと原型が分からなくなります。
この発展の仕方を「性格変奏」と呼びます。
ブラームス以後の作曲家による変奏曲に多いタイプです。
多くの楽曲は、この「単純変奏」と「性格変奏」の2つの組み合わせで構成されていることが多いのです。
まとめ
変奏曲は、1つのメロディーがこれでもかと形を変えるのが醍醐味の形式です。
聴いても良し。弾いても良し。
目まぐるしく変わる曲調・色彩を大いに味わいましょう。
音楽への見地を深めるために必要なこと
より深い音楽理解するため、
集中して音楽鑑賞すること、楽譜・スコアを読み込むことなどは非常に有意義ですが、
実際に楽器を演奏して音に出すことこそ、
音楽をより深く理解することにつながります。
いま、周りに音楽を教えてくれる先生がいない場合、音楽教室に通うのが近道かと思います。
名古屋周辺でしたら、クラブナージ音楽教室がオススメです!
音大卒の優秀なプロ講師が多く在籍する上、名駅・栄・今池と通える教室が豊富です。
気になった方は、一度体験レッスンを受けてみませんか。
先生一同・スタッフ一同、申し込みお待ちしております。
https://www.clubnagy-music.com/
忙しくてレッスンに通う事が厳しい方、または遠方の方へ
そんな方は、オンライン音楽教室のレッスングリッドがオススメです!
いつでも、どこでも、
最高の音楽レッスンが受けられます。
自宅からでも、早朝、深夜帯でも受講可能です。
気軽に話せるベテラン先生から、音大の先生、
きっとぴったりの先生が見つかります。
これからも、初心者から上級者まで 全ての音楽好きの方に役立つ情報発信をしていきたいと思います。
よろしくお願いします。